日本の年中行事、祝日、二十四節気を1月~12月まで月別にまとめました。
【祝日】
祝日とは、内閣府「国民の祝日に関する法律」に定められた国民の休日です。
その第一条には、『自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。』と定義されております。
*2020年の東京オリンピック開催年は、「海の日」「体育の日(スポーツの日)」「山の日」が特例で変更になります。
【二十四節気】
二十四節気とは、1年を太陽の黄道上の位置にしたがって24等分した中国伝来の季節区分です。節分を基準にするため、うるう年で日にちが前後します。
ニュースや天気予報でも話題にでたり、季節の挨拶に使う場合もありますので、日頃から意識していると空気の流れ、温度など、自然の変化を感じ取れますね。
◇行事
■1日~7日 御年賀
前年度御歳暮が間に合わなかった場合に贈る
■7日 七草がゆ
朝に春の七草を入れたおかゆを食べると万病を妨げ長寿を
願うという風習。松の内はこの日まで。門松注連飾りは
この日に取り外す。
■11日 鏡開き
鏡餅を下げてお雑煮やお汁粉にして食べる。もちは縁起
をかつぎ、切らずに開く(木づちで砕く、手で割る)。
■15日 小正月
小豆がゆでお祝いする日。別名「女正月」とも呼ばれ、
お正月に立ち働いた女性をねぎらう意味もある。
どんと焼きを行う事も多い。
◇祝日
■1日 元旦
「年のはじめを祝う」
初詣は松の内に済ませるものとされている。
神社仏閣では賽銭を賽銭箱に投げいれ、自分の穢れを
貨幣に移して身を清めるという意味
■第2月曜日 成人の日
「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうと
する青年を祝いはげます」
◇二十四節気
■6日頃 小寒(しょうかん)
次第に寒さが増してくるころ
■20日頃 大寒(だいかん)
寒さが一番厳しいころ
◇行事
■3日 節分
立春の前日。厄を祓い、福を招き入れるために、ひいらぎ
の小枝にいわしの頭を刺して家の戸口に飾り(やいかがし)、
豆まきをする。最近では恵方巻を食べる風習も一般化して
きた。その年の恵方を向いて太巻をまるかじりし、
食べ終わるまで一言もしゃべらない事で、無病息災で
過ごせると言われる。
鰯の臭いとひいらぎのトゲで鬼を追い払う。節分とは
本来季節の変わり目の事で。立春・立夏・立秋・立冬の
前日のことをいう。
■14日 バレンタインデー
ローマ司祭 バレンチヌスが処刑された日。彼は兵士の
結婚を禁じる掟を破り多くのカップルを結婚させた。
これにちなんで、欧米で恋人たちが贈り物を交換する
習慣が生まれたとされる。
日本では女性から男性への愛の告白にチョコレートを
あげる場合と、日常のお付き合いの感謝をこめてプレゼント
する場合とがある。
◇祝日
■政令で定める日 建国記念の日
「建国をしのび、国を愛する心を養う」
◇二十四節気
■4日頃 立春
暦の上では春
■19日頃 雨水(うすい)
草木の芽が出始める
◇行事
■3日 ひな祭り(桃の節句)
女の子の成長を願って祝う。ひな人形を飾るようになった
のは室町時代以降。一夜飾りは縁起が悪いとされ、節分が
終わったころに飾り、節句の翌日~3日以内に片付けると
される。はまぐりは「夫婦和合」の象徴とされお吸い物に
して祝う。
関東では向かって左が男雛、右が女雛。関西は逆が多い。
■14日 ホワイトデー
バレンタインデーに対応し、日本の菓子業界が広めた習慣。
バレンタインデーのお返しとして、クッキーやマシュマロ
を贈る日とされている。
■春分を中日とした7日間 春のお彼岸
仏壇をきれいにして、「ぼた餅」を供えます。寺院に参拝
したり、墓参りをするなどの仏事を行ったりもする。初日を
「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と呼ぶ。
■下旬 卒業式
◇祝日
■21日頃 春分の日
「自然をたたえ、生物をいつくしむ」
◇二十四節気
■6日頃 啓蟄(けいちつ)
冬眠していた虫が地中から出てくる
■21日頃 春分
昼と夜の長さが等しくなる
◇行事
■上旬 入学式 入社式
◇祝日
■29日 昭和の日
「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをいたす」
◇二十四節気
■5日頃 清明(せいめい)
春分から15日目。天地が清々しく、万物が生き生きする
■20日頃 穀雨(こくう)
穀物を育てる雨がふる
◇行事
■第2日曜日 母の日
母の日頃の苦労をいたわり、感謝をあらわす日。アメリカで
教会行事として始まったと言われ、敬愛した亡き母に捧げた
花がカーネーションであったことからカーネーションの花を
贈るのが定着した。
◇祝日
■3日 憲法記念日
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」
■4日 みどりの日
「 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、
豊かな心をはぐくむ」
■5日 こどもの日
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかると
ともに、母に感謝す」男の子の成長を願う祭りに
なったのは江戸時代から。菖蒲湯は尚武や勝負に
通じるとされ、鯉のぼりは成長と出世を祈って
立てるようになった。
◇二十四節気
■6日頃 立夏
暦の上では夏
■21日頃 小満(しょうまん)
草木が育ってあらゆるところに満ち溢れる
◇行事
■第3日曜日 父の日
父の日頃の苦労をいたわり、感謝をあらわす日。アメリカで
男手ひとつで6人の子供を育てた父への感謝がきっかけと
なった。白いバラを贈るとされているが日本ではあまり
白いバラは定着していない。
◇祝日
なし
◇二十四節気
■6日頃 芒種(ぼうしゅ)
稲・麦などの母の日頃の苦労をいたわり、感謝をあらわす日。
芒(のぎ)のある穀物の種をまく時期
■22日頃 夏至
一年で昼が最も長くなる日
◇行事
■7日 七夕
古代中国の牽牛と織女の伝説にちなんだ祭り。地方によっては
8月7日に行う所もある。(仙台の七夕等)江戸幕府が七夕を
五節句に定めた事から庶民に広まったと言われる。
笹竹は神聖で生命力があるとされる。
■上旬~15日 お中元
親戚、仲人、恩師、会社の上司、仕事の取引先、習い事の先生等、
公私に関わらず日頃御世話になっている人。
15日までに先方に届くようにする。金額は3000円~5000円くらい
が多い。
■15日~立秋(8月8日頃)暑中御見舞、暑中御伺
お中元を贈る時期を逃した場合に贈る。
目上の人に対しては暑中御伺とする。
■13~16日 お盆
先祖を供養する行事。仏壇の前に精霊棚を作って供え、13日の
夕方迎え火を焚いて先祖を迎え、15日か16日の夕方送り火で送りだす。
◇祝日
■第3月曜日 海の日
「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」
◇二十四節気
■7日頃 小暑(しょうしょ)
夏至の15日後。このころから次第に暑さが増し暑中に入る。
■23日頃 大暑(たいしょ)
最も暑いころ。暦の上では晩夏。
◇行事
■立秋(8月8日頃)~下旬 残暑御見舞
お中元、暑中御見舞の時期を逃した場合
■13~16日 旧盆
月遅れ盆ともいい、この日をお盆として過ごす地域もある。
(明治次第に旧暦から新暦に切り替えられたが、関東以外は
こちらの日程が多い傾向がある)
帰省ラッシュもこの時期が一番ピークとなる。
◇祝日
■11日 山の日
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」
◇二十四節気
■8日頃 立秋
暦の上では秋
■23日頃 処暑(しょしょ)
立秋から15日目。暑さが次第にやわらいでくる
◇行事
■秋分を中日とした7日間 秋のお彼岸
仏壇をきれいにして、「おはぎ」を供える。寺院に参拝したり、
墓参りをするなどの仏事を行ったりもします。初日を
「彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」と呼ぶ。
(春は牡丹の花にちなんで牡丹餅(こしあん)と言い、
秋は萩の花にちなんでおはぎ(つぶあん)と言う)
■半ばの満月の日 中秋の名月
「十五夜」と呼び、きれいな満月を観賞するならわし。
窓辺に月見だんご、里芋、果物、すすき、秋の七草を飾り、
五穀豊穣を祝う。
◇祝日
■第3月曜日 敬老の日
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し長寿を祝う」
■21日頃 秋分の日
「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」
◇二十四節気
■8日頃 白露(はくろ)
秋分の15日前。草木に露が見られ白く光る
■23日頃 秋分
春分と同じく昼と夜の長さが等しくなる
◇行事
■衣替え
明治時代に政府が6月1日と10月1日を衣替えの日と定
め、それが習慣として今日まで伝わっている。最近は温暖
の差もあり、その年の気候や人それぞれに行う事が多くな
り、いっせいに衣替えする事は少なくなってきた。
もともとは平安時代に、物忌みの日に御祓いの行事として
衣類だけでなく調度品なども入れ替えていた。
◇祝日
■第2月曜日 体育の日(2020年よりスポーツの日
「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」
◇二十四節気
■8日頃 寒露(かんろ)
秋分から15日目。草木に宿る露が冷たく感じられる
■23日頃 霜降(そうこう)
霜が降り始めるころ
◇行事
■15日頃 七五三
男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の年に、神社
や寺に参拝し、成長を感謝する行事。3歳の子が髪を伸
ばし始める「髪置き」、5歳の男の子が初めて袴をつけ
る「袴着」、7歳の女の子が着物のつけひもを帯に替え
る「帯解き」の儀式がもとになっている。
◇祝日
■3日 文化の日
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」
■23日 勤労感謝の日
「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう
◇二十四節気
■8日頃 立冬
暦の上では冬
■23日頃 小雪(しょうせつ)
小雪がちらつき始めるころ
◇行事
■上旬~20日頃 御歳暮
一年の感謝の気持ちを品物に託して贈る。お中元を
贈ったた方には必ず送る。お中元よりも格が上になる
ので、贈り物のランクを下げるのはマナー違反。
■25日 クリスマス
クリスマスカードは24日までに届くようにする。
海外ではクリスマスカードと年始の挨拶が一緒が一般
的。
◇祝日
■23日 天皇誕生日
「天皇の誕生日を祝う」
◇二十四節気
■7日頃 大雪(たいせつ)
雪が積もるほど降るころ
■22日頃 冬至
昼が最も短い日
六曜は中国で生まれたとされる歴で、日本で一般的に使われている。六曜で日を選んで、イベントの日時を決める経営者も多く、覚えておきたい一般知識の一つです。
・先勝・・・午前中は吉。午後は凶。何事も急いでするとよいとされる日。
・友引・・・朝晩は吉で、昼は凶。友を引くとして葬礼を避ける習慣がある。
・先負・・・午前中は凶。午後は凶。
・仏滅・・・何をするにも凶とされ、結婚式は避ける習慣がある。
・大安・・・何をするにもよいとされる吉日。
・赤口・・・正午のみ吉。それ以外は一日凶とされる。
自分のマナーに不安を感じたら
マナーの知識を得たら、後は実践あるのみ。
マナーの実践指導なら元ANA CA講師が指導するFINESTへ!
▼マナー研修のFINESTの公式HPはこちらから
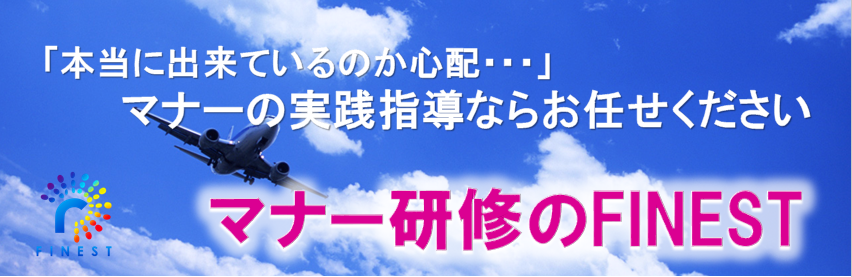
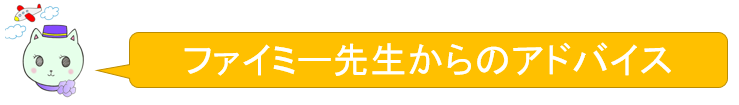
最近のコメント